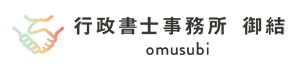遺言によって何ができるか|遺言が無効になるケースについて詳細解説
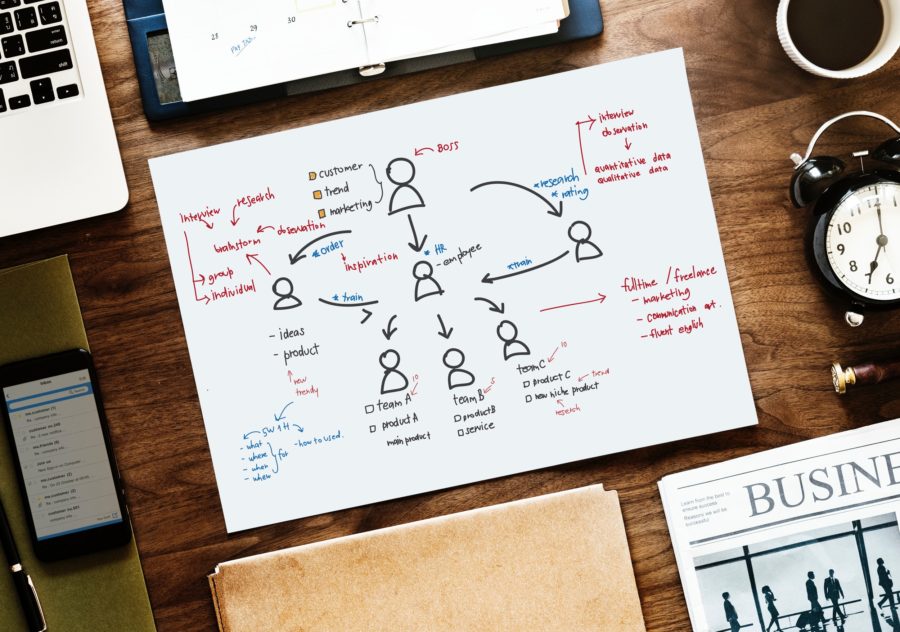
遺言によってできることは遺贈することだけではありません。
遺言によってできることを把握することで活用方法の幅もぐっと広がると思います。
なので、今回は、
について、解説していきます。
遺言でしかできないこと|遺言、生前行為双方でできること

(1)遺言でしかできないこと
- 相続分の指定又はその委託
- 遺産分割の方法の指定又はその委託
- 遺産分割方法の禁止
- 遺産分割する場合の相続人間の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定又はその委託
- 遺留分減殺の方法の指定
- 未成年後見人の指定又は未成年後見監督人の指定
相続分の指定に関して遺言は現時点で登記などでかなり強い効力を有します。
ex:甲建物について名義は被相続人AでAには、相続人がB、Cの二人(法定相続分は2分の1ずつ)いる例で説明します。
遺言で「甲建物をBに3分の2、Cに3分の1の割合で相続させる」としていたのに、Cが法定相続分の2分の1を第三者Dに贈与して登記している場合、Dが取得した2分の1をBに対抗できず、登記があっても、Dが取得できるのは、3分の1までになります。
しかし、さきほど現時点でといったのは、これが2020年7月の相続法の改正でかわります。
登記したDはBに対して法定相続分の2分の1を対抗できることになります。
Bは遺言で3分の2取得したのにもかかわらず、登記するのが遅かったばかりに、2分の1しか取得できないのです。
これは国が空き家などの問題が生じたときに相続人をたどれるようにしっかり相続登記をさせようという動きがあるといえます。
民法908条
被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることで第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない機関を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
民法911条
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
参考:「判例六法」有斐閣
(2)遺言、生前行為の双方でできること
- 子供の認知
- 相続人を廃除すること又は廃除の取消
- 相続財産の処分
- 一般財団法人設立する意思の表示
- 信託
廃除というのは、遺留分をもつ相続人=兄弟姉妹以外が被相続人に虐待や重大な侮辱をし、その者自身が著しい非行があったとき被相続人が家庭裁判所に請求することで、その者の相続権をはく奪することをいいます。
信託とは、特定の者(受託者)が一定の目的(受託者の利益は除く)に従って財産の管理、処分、その他目的のために必要な行為をいいます。
御結では遺言、相続に関する業務も承っております。
遺言の能力が認められる者

遺言をできる年齢は15歳になれば未成年であっても、できます。
15歳未満がしたものはどうなるのかというと、無効です。
これは、法定代理人の同意があっても有効となるものではありません。
では制限行為能力者はどうなのでしょうか?
成年被後見人は、事理弁識能力が一時的に回復した時であれば、医師2人以上の立会のもとで有効に遺言をすることができます。
成年後見人が代理してはできません。
他の制限行為能力者はといいますと、被保佐人、被補助人の双方とも、一人で有効に遺言をすることができます。
遺言を残したあとに、遺言能力がなくなったとしても、遺言自体が無効になることはありません。
民法960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
民法961条
15歳に達した者は遺言をすることができる。
民法963条
遺言者は遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない。
参考:「判例六法」有斐閣
遺言が無効になるケース

よくあるケースを紹介いたします。
- 遺言に記載した財産を生前行為によって贈与、売買してしまった場合
- 共同遺言をする
- 日付の記載を吉日と記載
1のケースではその財産の部分だけ遺言が無効となり、それ以外の遺言の記載は有効のままです。
また、錯誤の状態で贈与行為をしてしまった場合は、その財産の贈与に関し、無効を主張することができ、遺言の記載が無効とはなりません。
2のケースでは、共同で遺言を1枚の紙に部分を区切って書いたとしても、無効です。
一つの証書を切り離せば別々になる場合は遺言書の効力は有効となります。
また、別人が書いた遺言書が一つの封筒から出てきたといった場合も遺言書の効力は有効です。
3のケースは日付が確定できないため、無効となる案件です。
特定さえできればいいので、2020年東京オリンピック開催式の日など特定できるものは有効となります。
民法975条
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない。
参考:「判例六法」有斐閣
まとめ

遺言の活用を知ることで、可能性が広がったのではないでしょうか。
ただ、遺言の活用方法が、相続に関することだけではないのは、意外ですよね。
また、遺言を正しく知ってうっかり、遺言が無効とならないようにしていただければと思います。