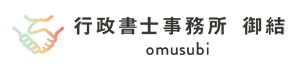これでわかる!農地転用をケースごとに紹介・詳細解説|賃貸借編

前回の記事では、農地転用の所有権移転のケースについて、お話いたしましたので、今回は、賃貸借について解説・ケース紹介をしていきたいと思います。
目次
- 市街化区域での転用の場合、農地の賃貸借の解約の可否
- 農地の賃貸借の期間50年間での申請の可否
- 賃借人の帰責事由による契約解除を理由に農地法18条の許可や賃借人の同意ない場合の農地の返還の可否
- 農業委員会の和解の仲介による農地の所有権移転の場合の農地法3条の許可の要否
- 農事調停による農地の所有権移転の場合の、農地法3条の許可の要否
- 農地の使用貸借に関して借受人の死亡により相続
- 賃借人の死亡により耕作が不継続時の貸付け期間中の解約の可否
- 賃貸人の死亡により賃貸借の解約
- 疾病で一時的に耕作できない場合の賃借している農地を転貸の可否
- 農地の使用貸借の貸付け期間の満了での解約の可否
- 農地法3条の賃貸借で貸付け期間の満了により許可を得ずに解約できる方法の有無
- (市街化区域以外の)農地の賃貸借で貸付け期間満了により解約となる法律の手続きの有無
- 10年間未満の農地の賃貸借は貸付け期間が満了時の解約に賃借人の同意や農地法の許可の要否
農地転用の許可の要否・ケース別考察

(1)市街化区域での転用の場合、農地の賃貸借の解約可否
農地法3条等による農地の賃貸借において、法18条の許可を得て解約ができる要件の一つに「その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合」とあり、さらに「法18条第2項第2号に該当するかは、例えば、具体的な転用計画があり、転用許可が見込まれ、かつ、賃借人の経営及び経営状況や離作条件等からみて賃貸借契約を終了させることが相当と認められるか等の事情により判断するものとする」と、農林水産省の通知に示されています。
以上のことから、農地が市街化区域にある場合には、農地転用の手続きは届出で足り、転用計画が実現性が認められることから離作条件などが適当であると判断されれば、法18条の許可を得ることができます。
(2)農地の賃貸借の期間50年間での申請の可否
民法604条1項が改正により、賃貸借の期間が20年から50年から改正され、民法の観点からも可能となりました。
改正前であっても、農地法の規定で「農地又は採草地の賃貸借についての民法第604条の規定の適用については、同条中「20年」とあるのは、「50年」とあるため、可能ではありました。
(3)賃借人の帰責事由による契約解除を理由に農地法18条の許可や賃借人の同意ない場合の農地の返還の可否
法18条において「農地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をしてはならない」と規定されており、農地の返還を受けることができません。
この場合、法18条の許可申請をしますと、許可基準に「賃借人が信義に反した行為をした場合」と規定されていることから許可を得ることができます。
(4)農業委員会の和解の仲介による農地の所有権移転の場合の農地法3条の許可の要否
法3条の農地の賃貸借の解約は、法18条の許可等が必要となります。
そのため、時折、賃貸人と賃借人との間で農地の賃貸借の解約について紛争になるケースがあります。
この紛争の解決の手段としては、
- 農事調停
- 農業委員会・知事による仲介
- 裁判
等があります。
②の農業委員会の和解の仲介は、地域の事情を知る農業委員会が仲介することによって、解約の合意に向かいやすいというメリットがあります。
その農業委員会の和解の仲介により、賃貸している農地等の一部を賃貸人が賃借人に譲渡することで解約の和解が成立した場合は、農事調停と異なり、法3条の例外規定とされていないため、法3条の許可が必要となります。
また、農地を引き渡すことになる期限前6か月以内の合意であることを前提とすると、法3条の許可等を申請する前に、法18条6項の規定による通知書を農業委員会に提出することが必要となります。
(5)農事調停による農地の所有権移転の場合の農地法3条の許可の要否
法3条による農地の賃貸借の解約は、法18条の許可等が必要となります。
そのため、時折、賃貸人と賃借人との間で農地の賃貸借の解約について紛争となるケースがあります。
この紛争の解決の手段としては、
- 農事調停
- 農業委員会・知事による仲介
- 裁判
等があります。
そのひとつである農事調停は、民事調停法において、民事調停の特則として設けられている調停の一つで調停委員が介入し、合意に基づく解決を図るための制度となります。
手続きは、原則として地方裁判所に調停の申立てをして、その後、調停が成立した場合には、裁判による判決と同じ効力を持ちます。
農事調停において解約の補償として、賃貸している農地の一部を賃貸人が賃借人に譲渡することで合意する場合は、農地法の規定により、農地の所有権移転については、法3条の許可が不要となり、調停調書により、農地の所有権移転が可能となります。
(6)農地の使用貸借は借受人の死亡により相続
a.借受人の死亡
使用貸借は、民法599条により「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」と規定されています。
よって、使用貸借を目的とした法3条の許可及び農業経営基盤強化促進法の利用権設定等で借り受けている農地は、ともに借受人の死亡により使用貸借は終了することになります。
耕作を引き継ぐなどの場合には、再度使用貸借契約を農地の所有者と締結し、法3条の許可等を得ることが必要となります。
b.貸付人の死亡
一方、貸付人が死亡した場合には、民法599条により、使用貸借は終了しないため、使用貸借の期間満了まで継続されることになります。
また、農地を相続したときには、農業委員会に法3条の3の権利取得の届出を行う必要があります。
(7)賃借人の死亡により耕作が不継続時の貸付け期間中でも解約の可否
農地の賃借権は、原則として、相続の対象となります。
ただ、相続人が耕作をする意思がない場合には、6か月以内に農地を引き渡すことを書面で明らかにした合意解除を行うことが推奨されます。
その時の手続きとしましては、耕作を引き継がない農地の賃借権について、相続人を確定させることは難しいと考えられるため、法定相続人全員で賃貸人と合意解除をし、法18条6項の規定による通知書を農業委員会に提出するという」手段をとることになります。
(8)賃貸人の死亡による賃貸借の解約の可否
賃借権は、被相続人の一身専属権ではないため、相続の対象となるため、賃貸人の死亡によって賃貸借は、解約されません。
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画により、第三者に賃貸している場合には、貸付期限が到達するまで農地が返還されません。
また、法3条による農地の賃貸借は、法18条の許可等を得ないと、貸付け期限が到達しても、引き続き賃貸借が継続されることになります。
農地の権利等を相続した時は、農業委員会に法3条の3の権利取得の届出を行うとともに、法3条により賃貸借をしている農地については、賃借人との契約書の氏名等の変更を行う必要があります。
(9)疾病で一時的に耕作できない場合に賃借している農地を転貸することは可能か否か
借り受けている農地を転貸することは、法3条2項6号により禁止されています。
しかし、例外として、下記の場合には、転貸ができます。
- 耕作者及びその世帯員等の死亡又は疾病や負傷の療養により耕作ができないため、一時的に貸し付ける場合
- 耕作者が世帯員等に貸し付ける場合
- 水田裏作の目的に供するため、貸し付ける場合
上記の場合であっても、民法612条1項に「賃借人は、賃貸人の承諾が得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」と規定されているため、転貸する際には、賃貸人の承諾が必要となります。
また、転貸には、法3条の許可を得る必要があるため、借受人は許可要件を満たすことが必要となります。
(10)農地の使用貸借は、貸付け期間の満了で解約となるか
法3条の許可を得て、貸付け期間を定めた農地の使用貸借による権利の設定を行った場合は、その期限が到達した時に使用貸借は解約となります。
但し、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による利用権設定等の場合と異なり、市町村や農業委員会から、原則、事前にその期限が到達するといった連絡などはありません。
そのため、期限が到達しても、農地をそのまま貸し続けてしまうことがあり、無断の貸付けとなるのみならず、一定期間を経過する時効取得となる恐れがある点に注意が必要です。
(11)農地法3条の賃貸借で貸付け期間の満了により許可を得ずに解約できる方法はあるか
法3条許可による期間の定めのある賃貸借について期間満了により解約をする場合は、法18条の都道府県知事の許可を得て、その期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をすることが必要です。
一方で、更新をしない旨の通知において、都道府県知事の許可が例外的に不要であるものとして、10年以上の期間の定めのある賃貸借があります。
よって、賃借人と10年以上の期間の定めのある賃貸借をすることで法3条の許可を得て、その期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知を行えば、都道府県知事の許可を得ずに賃貸借が解約されることになります。
(12)(市街化区域以外の)農地の賃貸借で貸付け期間満了により解約となる法律の手続きはあるか
市街化区域外の農地について、一部地域を除いて、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による利用権の設定という方法があり、利用権の設定により農地を賃貸借した場合は、貸付け期間が満了になると同時に解約となります。
賃貸借を更新する場合は、市町村より事前に更新の有無の連絡があるため、再度、更新の手続きを行うこととなります。
農業経営基盤強化促進法の利用権設定等促進事業が、認定農業者や認定就農者等の担い手に農地を集積するため市町村が農用地利用集積計画を作成し、農地の利用を進めようとするもので、貸付け人と借受人は、その計画に同意するという手続きををとります。そのため、両者の間に契約行為はありません。
さらに農業振興地域であれば、農地中間管理事業が市町村に農地利用集積円滑化団体があれば、農地利用集積円滑化事業による利用権設定という制度があり、同様に貸付け期間が満了になると、同時に賃貸借が解約されます。
(13)10年間未満の農地の賃貸借は貸付け期間が満了しても解約に賃借人の同意や農地法の許可が必要か否か
法3条の許可による農地の賃貸借の設定は、期間の定めのある場合において、その当事者がその期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、原則、従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借をしたものとみなすと規定されています。
また、賃貸借の更新をしない旨の通知をする際は、都道府県知事の許可が必要となり、その許可要件として、賃借人が信義に反した行為をした場合等と規定されています。合意による解約については、その解約については、その解約によって農地等を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものについて農業委員会に通知した場合は、賃貸借の解約と通知はいりません。
まとめ

今回は、農地の賃貸借の場合の転用について、紹介いたしました。
所有権移転の場合は、所有権移転の記事をご覧ください。