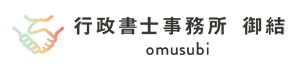これで安心!任意後見制度とは|詳細解説

任意後見について、法定後見との兼ね合いや信託などよく似て非なるものがあり、わかりづらいので、任意後見に絞って解説していきたいと思います。
目次
1. 任意後見制度の概要

(1)現行の任意後見制度
現行の任意後見制度は、平成11年の成年後見法改革に際して、本人の自己決定の尊重と本人の保護との調和を図る観点から新たに導入された制度となります。
すなわち、監督人や裁判所による監督のもと、本人の意思に基づき権限を付与された後見人が本人の財産管理を行うというものとなります。
本人は、任意後見契約の発効後も、自身の行為能力をなんら制限されることがないため、後見人による契約とは無関係に単独で契約を締結することができます。
本人の保護(監督)の要素を残しつつも、最大限、本人の自己決定の尊重を図る制度設計を考えられているものであります。
(2)任意後見組織とその特徴
任意後見制度が想定する後見組織は、本人・任意後見人・任意後見監督人の三者によって構成されます。
・本人
本人は、任意後見契約の委任者となるもので、少なくとも、契約時においては、事理弁識能力が不十分な状況にいまだ陥っていないことが要求されます。
よって、先天的に判断能力を欠く者が任意後見制度を利用することは想定されておらず、その場合は、法定後見制度の利用が選択されるのが一般的であります。
なお、任意後見契約においては、契約の発効後も、本人が財産管理能力を奪われることはなく、任意後見においては、契約の発効後も、本人が財産管理能力を奪われることはなく、任意後見人の援助を得ずに本人独自の判断で取引を行うことがなお可能となります。
その反面、悪徳商法等による被害の救済は、民法・消費者契約法等が定める一般法理に頼らざるを得ないこととなってしまいます。
・任意後見人
任意後見人は、本人との間で任意後見契約を締結する相手方たる受任者に当たるものになります。
本人の生活、療養看護及び財産管理に関して付与された一定の代理権を用いて任務を遂行することになります。
代理権を用いたリーガルサービスが業務の中心であって、本人の介護といった事実上の業務は対象とならない反面、いわゆる移行型の任意後見契約において、発効前であっても一定の財産管理や身辺の見守りを引き受ける場合や、いわゆる死後事務委任として、本人の死後において遺産の管理を一部引き受ける場合があります。
本人の親族が受任するケースが多いものの、最近は、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門家が受任して任意後見人となるケースが増加しています。
・任意後見監督人
任意後見監督人は、任意後見契約の当事者ではないが、任意後見人の事務を監督し、この事務に関して家庭裁判所に定期的に報告する任務を負う者として、家庭裁判所が選任するものになります。この選任を経ないと契約を発効しないものとして監督人の設置を必須化し、不正行為回避の強化を図っているのが、任意後見制度の大きな特徴となっています。
(3)任意後見実務に関与する専門家
任意後見契約は、通常、その締結から発効までの期間が不確定であり、そもそも判断能力が低下しないために発効しないケースもみられることから、任意後見契約の締結段階と発効段階とで手続きが大きく2分化されています。
そして、締結段階の手続きでは本人の契約締結意思が、発効段階の手続きでは、本人の判断能力の低下が、それぞれ慎重に判断されなければならないため、前者につき公証人、後者につき裁判所という公的機関を関与させるなどの規律を与えています。
したがって、任意後見制度の利用にあたっては、以上の三者のほかにも、手続きの流れにそって様々な専門家が関与することになります。
本人の立場からは、任意後見契約の締結前に専門家による相談を経るのが通常であるから、本人の人生設計、財産管理に関する本人の意向を聴取し、その意向に沿った財産管理制度の選択をしなければならないため、それには専門家の関与が望ましいからであります。
すなわち、任意後見制度以外にも一般の財産管理委任契約や法定後見制度、さらには近時注目されている信託契約の利用も考えられるため、専門家としてはこれらの制度との比較において、適切な選択へと本人を導く必要があります。
第1に任意後見契約は、公正証書によってしなければならないため、公正証書の公証人が手続きに関与することになります。
第2に制度の利用の前提として、任意後見契約の登記を経由しなければならないため、登記官が関与することになります。
第3に、本人の判断能力の低下後は、裁判所による任意後見監督人選任の条件として、その低下を証明する診断書を作成しておかなければならないため、精神科医が手続きに関与することになります。
第4に任意後見契約の発効段階の前提となる任意後見監督人の選任を行います。この手続きには、家庭裁判所の裁判官が関与することになります。
以上の手続きにより任意後見契約が発効すると、本人が契約を締結した相手方である任意後見人が財産管理の職務に着手することになります。
この任意後見人には、一般的に職務の専門性から行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士等が就任することが多いです。
そのほかにも、任意後見契約そのものではなくても、これに関連する役割を担うものとして、福祉型信託契約における受託者である信託銀行や、公正証書遺言において指名される遺言執行者、日常生活自立支援事業の利用契約の相手方である社会福祉協議会、介護関係の契約の相手方である介護サービス提供業者といったものがこれに当たります。
(4)任意後見法の所在
任意後見法の所在としては、まず任意後見契約に関する法律を中心とし、それ以外にも、任意後見契約の基礎たる委任契約、及び任意後見監督人などにつき一部準用される後見規定を置く一般法としての民法、また、任意後見契約公正証書を作成する場面では、任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令や公証人法、公証人手数料令、任意後見契約の登記の場面では、後見登記法や後見登記等に関する政令・省令、任意後見監督人の選任の場面では、家事事件手続き法や家事事件手続き規則がそれぞれ関連する規定があります。
また、法務省が発する各種通達の存在の中に重要なものがあり、それというのは「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取り扱いについて」と「後見登記等に関する法律等の施行に伴う後見登記等に関する事務の取り扱いについて」の存在が挙げられます。
2. 任意後見と類似する制度

(1)任意後見契約の性質
任意後見制度は、平成12年4月に施行された任意後見法により創設されたものであるが、それ以前に自らの財産管理や身上監護を特定の他人に委ねる制度がなかったわけではなく、民法上の委任の契約を締結して、任意代理人を選任するという方法があります。
委任契約とは、ある者が法律行為をすることを他人に委託する契約であり、その委託する内容は合意によって定まります。
民法は、法律行為以外の委託も準委任契約として、委任契約の規定を準用しているので結局委任契約において委託する内容はどのようなものでもよいこととなり、契約などを伴う財産管理のみならず、介護行為そのものを委託することも条文上は可能となります。
そして、この委任契約の終了事由には、契約解除など当事者の意思により終了させるほかに、「委任者又は受任者の死亡」「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」「受任者が後見開始の審判を受けたこと」が定められているが、委任者の意思能力または行為能力の喪失は挙げられていません。
また、委任契約によって委任を受けた受任者は、その委託内容について代理権を授与されたことになりますが、民法は代理権が消滅する事由として、「本人の死亡」および「代理人の死亡または代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと」を挙げ、さらに委任による代理権は「委任の終了」によって消滅すると定めるのみであるから、任意代理権の消滅事由にも本人の意思能力及び行為能力の喪失は含まれていません。
すなわち、民法上の委任契約によって財産管理等を委託した場合、本人の判断能力が低下した場合にも委任契約は終了することなく、任意代理権も消滅いないということになります。
以上のことからなぜ、民法の委任契約があるのに、任意後見制度が創設されたのかという疑問が浮き彫りになります。
その答えとして、本人の判断能力が低下した後における本人の保護のための制度が手当てされていなかったということによります。
すなわち、委任契約を締結した後に本人が意思能力を喪失したような場合には、受任者は本人の意思を確認することができなくなり、本人の意思にそった財産管理等が難しくなります。
それだけでなく、本人が受任者の行動をコントロールできなくなることにより、受任者が権限を濫用することも考えられます。
このような問題点は、従来から指摘されてきたところであるが、いよいよ我が国高齢社会を迎えるにあたって高齢により判断能力が低下した場合に特化した委任契約として特別に定められたものが任意後見制度となります。
(2)任意後見契約の特殊性
本人の判断能力が低下した後の本人の財産管理や身上監護を目的とする特殊な委任契約である任意後見契約の具体的な特殊性は、要件において、①要式契約とされている点、及び効果において②効力発生が家庭裁判所による任意後見後見人に対する監督がある点にみられます。
ア.契約の様式性
任意後見契約の締結は、制度の利用者である本人と、任意後見人との間でなされる点は、通常の委任契約と同じであるが、法務省令で定める様式の公正証書によって締結する必要があり、公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がされます。
公証人とは、裁判官、検察官等の実務経験を有する法律実務家のなかから法務大臣が任命する公務員で全国の都道府県に300余り設置されている公証人役場で職務を行っており、その公証人によって作成した公文書であり、訴訟における証明力が強く、一般の委任契約についても公正証書によって締結することは可能であるが、契約の成立には意思表示の合致のみがあれば足り、通常は契約締結の証拠として当事者間において契約書が交わされるのみであることが多いが、任意後見法があえて公正証書を義務付けることの意味としては、公証人という公的な、しかも法律実務経験者である関与することで委任する本人の意思能力の確認が期待できる点にあります。
一般の委任契約も任意後見契約も、契約である以上、意思能力がなければ無効となるところ、公証人26条や公証人法施行規則13条1項で意思能力の確認が義務付けており、また、任意後見公正証書の作成の際には原則として本人と公証人が直接面接することが必要とされている点も意思能力の確認を確実とさせています。
公証人法
26条
公証人は法令に違反したる事項、無効の法律行為及び行為能力の制限によりて取り消すことを得べき法律行為に付証書を作成することを得す
公証人法施行規則
13条1項
公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない
イ.任意後見監督人の選任による効力発生
一般の委任契約は、当事者がその効力の発生について特に条件を設けないかぎり、契約の成立とともに効力が発生し、受任者は委任者のための事務を遂行する権利を得て義務を負うこととなります。
これに対し、任意後見契約は、任意後見監督人の選任によってその効力が発生するため、任意後見監督人の選任があって初めてということになります。
前述のとおり任意後見制度は受任者の権限乱用を防止することを目的に創設されたものであるところ、任意後見人を監督する者が選任されることを効力の発生要件としたものとなります。
任意後見監督人の選任は、任意後見契約が締結、登記された後に、本人が「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況」になったときに、「本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者」の申立てによって家庭裁判所が行います。
この申立てをするには、本人以外の者がする場合または本人がその意思を表示することができない場合を除いて、本人の同意を必要とし、後見監督人を選任して任意後見契約の効力を発生させることについての事前の本人の同意を意味し、誰を任意後見監督人にするかについての同意ではありません。
また、任意後見監督人による監督を適正かつ実効的にするために、任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は任意後見監督人となることはできないとされており、また、これ以外にも監督人としての適格性を確保するために、未成年者や破産者、本人との争訟関係にある者や行方の知れない者なども任意後見監督人の欠格事由とされています。
ウ.任意後見人に対する監督
上記のように選任された任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告することを主たる職務とします。
任意後見人に対する監督のために、任意後見監督人はいつでも、任意後見人に対し、任意後見人の事務の報告を求め、または任意後見人の事務もしくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命じることができます。
これにより、任意後見人が本人の財産の管理を委託されているような場合には、その支出の使い途や出入について、厳正にチェックすることになります。そして、任意後見監督人が定期的に家庭裁判所へ報告することを義務付けることで、任意後見人は、家庭裁判所による間接的な監督を受けることになります。
さらに、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない自由があると認めるときは、任意後見監督人は家庭裁判所に対して任意後見人の解任を請求することができます。
(3)任意後見か一般の委任の契約か
上記のことを前提に、財産管理や身上監護を特定の他人に委託する場合に、任意後見契約によるべきか一般に委任契約によるべきかを選択する際には、何がポイントとなるのでしょうか。
まず、両者は、ともに契約であるという点では共通しているので、契約の時点で当事者に意思能力が必要となります。
一般の委任による場合であっても、受任者の権限濫用を防止するために、契約内容に監督者を置く旨を定めておく、あるいは委任契約の当事者に監督者も入れて締結するなど契約の中に監督に関する取り決めをいれておくことが望ましく、意思能力の有無が問題となるほどではないが、既に判断能力がある程度低下しているような場合、すなわち法定後見であれば補助制度の対象となるような状況であっても、法定後見を選択せずに、任意後見制度によることは可能であるため、本人保護のための制度が整備されている任意後見契約を選択したほうがいいと考えられます。
一方で、身体障害者等判断能力にはまったく問題はないが、日常生活に不自由がある者の財産管理や身上監護については、一般の委任契約によるしかないため、このような場合には、契約の中に監督による取り決めを入れておくのがいいと考えられます。
以上のことから任意後見契約か、一般の委任契約かの選択は、財産管理や身上監護の委託を開始する時点の本人の判断能力の有無を基準にすることが基本となるが、本人やその周囲の事情を考慮しながら、両方の契約を組み合わせたり、など柔軟に活用することがよいと考えます。
3. 任意後見契約の3つの種類

(1)移行型の任意後見契約
移行型の任意後見契約とは、通常の任意代理の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、当初は前者の契約に基づく財産管理等を行い、本人の判断能力低下後は後者に移行して、任意後見事務を行うことを想定した形態になります。
前者の任意代理の委任契約では、主として、本人の健康状態等を把握するたえmの見守り事務、財産管理事務、身上監護事務を任意後見受任者が行います。
このうち財産管理事務及び身上監護事務は、本人の判断能力または身体能力が低下した場合に、必要に応じて、必要な範囲で任意後見受任者が行うものになります。
よって、本人の判断能力の低下は、任意代理の委任契約の終了事由ではないため、本人の判断能力が低下して任意後見契約が発効することになっても、任意代理の委任契約はそのまま存続することになります。
しかし、その場合に任意代理の委任契約を存続させるのは、無意味となるため、任意後見契約の発効を任意代理の委任契約の終了事由とする旨の契約条項を盛り込んでおくことが必要となります。
(2)即効型の任意後見契約
即効型の任意後見契約とは、、任意後見契約の締結後、直ちに任意後見監督人の選任の申立てを行う形態となります。
本人の判断能力が低下したからこそ任意後見監督人の選任の申立てを行い、任意後見契約を発効させるにもかかわらず、ほぼ同時期に、任意後見契約を締結するだけの判断能力が本人にあるというのは、矛盾しているようにも感じられますが、それでも、即効型の任意後見契約が認められている理由は「軽度の痴呆・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度の対象者でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能」であるとされています。
任意後見契約を発効させる要件が「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」とされ、補助制度の対象者も含まれていることから意思能
力がある限り、任意後見契約を締結することが可能なうえに、直ちに任意後見契約を発効させることも可能です。
判断能力が低下している者が任意後見契約を締結することは、原則として、できないと考えるべきであり、即効型の任意後見契約も原則としてできないと考えるべきであり、そのように考えても、本人の判断能力が低下している以上、必要に応じて補助制度を利用することでサポートは可能となります。
この点につき、以下の4点をチェックして補助開始の審判の申立てを選択すべきとされています。
- 本人に任意後見契約締結に必要な意思能力があるのか。
- 本人は任意後見制度を理解しているか。
- 本人が任意後見契約を締結したいという積極的な意思を有しているか。
- 本人が契約の内容に自分の希望を反映させる意欲をもち、積極的な検討を行っていたか。
以上の4点を掲げ、原則として即効型の任意後見契約を容認しない考え方が提唱されています。
(3)将来型の任意後見契約
将来型の任意後見契約とは、本人jの判断能力が低下する前における財産管理や身上監護事務を行うことを内容とする任意代理の委任契約を締結せずに、任意後見契約のみを締結し、本人の判断能力の低下後に任意後見人のサポートを受けることのみを契約内容とする形態になります。
4.任意後見契約の委任事項

(1)法定の委任事項
任意後見法2条1項は、任意後見契約を「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」であると定義しています。
よって、「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部」が任意後見契約における法定の委任事項となります。
(2)財産管理に関する法律行為
財産管理に関する法律行為には、預貯金の管理や払い戻し、不動産その他の重要な財産の管理・処分、遺産分割、賃貸借契約の締結や解除等があります。
また、これらの法律行為に関連する登記や供託の申請等の公法上の行為も代理権の対象となります。
(3)身上監護に関する法律行為
身上監護に関する法律行為には、介護契約等の福祉サービス利用契約、医療契約などがあり、これらの法律行為に関連する要介護認定の申請等の公法上の行為も代理権の対象となります。
(4)訴訟委任
財産管理に関する法律行為や身上監護に関する法律行為に関して紛争が発生し、弁護士などに訴訟行為を依頼する場合がありますが、任意後見契約の締結時には、将来発生するかもしれない紛争を特定することは不可能であるので、任意後見契約書に盛り込むとしても、抽象的な訴訟代理権の授与とならざるをえません。
一般に訴訟委任においては、委任する事件および訴訟追行の目的を特定することが必要であるが、任意後見契約における訴訟委任の場合には、任意後見監督人および家庭裁判所の監督により訴訟代理権の濫用の余地がほとんどないこと、また、任意後見契約における訴訟委任の内容によって訴訟代理権の有無・範囲が明確にできることから、委任する事件および訴訟追行の目的を特定しなくてもよいと考えられています。
よって、代理権目録において実体法上の代理権を掲げたうえで訴訟委任については、以上の各事項に関して生じる紛争の処理に関する一切の事項などと記載するのが、実務の常識とされています。
(5)任意後見契約として委任できない事項
任意後見契約における委任事項は法律行為に限られ、事実行為は含まれません。
介護行為などの事実行為や婚姻・任意などの身分行為等は、任意後見契約として委任できません。
さらに、任意後見法2条1号より、「自己の」事務でない事務も、任意後見契約における委任事項となりません。
また、死後の事務も任意後見契約として、委任できません。本人の死亡により任意後見契約が終了してしまうからであります。
よって、死後事務に関する条項は、契約書の本文中に盛り込むことはできるが、代理権目録の中に記載することはできません。
5.任意後見契約に関する死後の事務

(1)死後の事務の位置づけ
本人の死亡により任意後見契約が終了してしまうので、死後の事務は任意後見契約における委任事項にはならないと解されているが、現実には、本人の死後においても、任意後見事務に関する処理の経過等を本人の相続人に報告しなければならないし、本人から預かった物があれば、これを本人の相続人などに引き渡す必要があります。
本人に親族がいない場合には、遺体の埋火葬や葬儀の手配をしなければならないこともあります。
病院や施設への支払いが残っている場合には、任意後見人は本人の預かり金の中から支払いをすることが多いといわれております。
また、任意後見契約も委任契約の一種であるので、こうした死後の事務のうち、任意後見人に報告義務があるのは、明らかであると言えます。
すなわち、任意後見人は本人の死亡により任意後見契約が終了したときには、任意後見事務に関する処理の経過と結果を本人の相続人に報告しなければならない。
また、本人の死亡により任意後見契約が終了するから、任意後見人は終了の登記の申請もする必要があります。
(2)応急処分義務
民法上の手がかりとしては、第1に応急処分義務があります。
これは、委任が終了した場合に、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるまで、必要な処分をしなければならないとされています。(法定後見では、成年後見人にこの義務が課されている)
応急処分義務は権限ではなく、義務であるため、これを怠ると、任意後見人は相続人等から損害賠償責任を追及されるリスクがある点に注意すべきです。
(3)事務管理
民法上の手がかりの第2として、事務管理があります。
事務管理は、義務なく他人のために事務の管理を始めた者はその事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によってその事務の管理をしなければならないとするものであります。
事務管理を行う者は、本人の意思を知っているとき、または推知できるときはその意思に従って事務管理をしなければなりません。事務管理を行った者は、費用償還請求権はありますが、報酬請求権はありません。
(4)死後の事務についての委任契約
委任契約は、委任者の死亡により終了しますが、自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がなされた場合には、委任者の
死亡によっても委任契約は終了しない旨の合意が含まれており、民法653条はこうした合意を否定するものではないとされています。
よって、死後の事務を、任意後見人に依頼したい場合には、死後の事務についての委任契約を、任意後見契約とは別に締結する必要があります。
(5)死後の事務の委任契約と本人の相続人との関係
死後の事務について任意後見人に依頼した場合には、相続人との関係に留意する必要があります。
すなわち、本人の権利義務は本人の死亡により相続人に承継されているので、たとえば、任意後見人が本人の財産を債務の支払いに充てるということは、実質的には相続人の財産を処分していることになってしまうからです。
また、死後の事務について委任契約が有効であるとしても、委任契約はいつでも解除できるので、本人の地位を承継した相続人がいつでも当該委任契約を解除することは可能となります。こうした事態を回避するには、死後の事務に関する委任契約の条項に、委任者からの解除権の放棄する旨を記載しておく必要があります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
高齢化社会が進んでいく現代において、自分にふさわしい制度を選んでいくことこそが正しい終活ではないかと考えております。