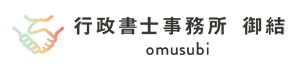賃貸借における民法改正点を詳細解説

2020年4月に民法改正がなされます。賃貸借に関してはほとんど今までの判例法理を明文化するものがほとんどですが、判例紹介を混ぜながら解説していきたいと思います。
目次
- 存続期間に関する改正
- 賃貸人の地位に関する改正点
- 不動産の賃借人の妨害排除請求権の明文化
- 敷金に関する改正点
- 賃借物の一部滅失による賃料の減額等
- 全部滅失による賃貸借終了に関する規律の明文化
- 賃借人の原状回復義務の明文化
- 転貸の効果に関する整備・明文化
- 賃貸借における損害賠償等についての期間の制限
1.存続期間に関する改正

改正前民法は、長期にわたる賃貸借は目的物の所有者にとって過度の負担となり得るため、存続期間を20年に制限していました。
しかし、20年を超える賃貸借の存続期間を定めるニーズがあり、経済活動上不都合である一面もあることから、20年を超えるものについては、永小作権・地上権を利用することで補うものとしていたものの、実際それらの利用はほとんどなく、賃貸借の存続期間を引き延ばす必要性があるため、今回の改正に至ることとなりました。
(1) 旧法のおさらい
・賃貸借の存続期間
最長期間: 20年
最短期間: 制限なし
例 外 : 短期賃貸借(602条)
※期間の定めのない場合は解約申入れされた後、次の猶予期間が認められます。
土地:1年 建物:3か月 動産:1日 (617条)
・借地権の存続期間
最長期間: 制限なし
最短期間: 30年
例 外 : 定期借地権(借地借家法22,23,24条)
※期間の定めのない場合:30年
・借家権の存続期間
最長期間: 制限なし
最短期間: 1年未満のものは期間の定めのないものとなる。
例 外 : 定期借家権、取り壊し予定の建物の賃貸借
(借地借家法38、39条)
※期間の定めのない場合は解約申入れされた後、正当な事由を有する時に猶予期間として6か月間認められます。
・契約期間の更新
賃貸借契約の期間の更新は借地借家法の規定によって修正されています。
・借地契約の更新の修正
①合意による更新・・・更新日から10年(最初の更新については20年)
当事者によりこれより長い期間の定め可能
②借地権者の請求による更新:
存続期間満了する場合、借地権者が契約の更新の請求をしたとき、建物がある場合に限り、従前と同じ条件で更新したものをみなします。設定者が遅滞なく異議を述べた場合は更新したものとみなされません。※
※借地設定者の異議が認められる場合
土地の使用を必要とする事情、借地に関する従前の経過、土地の利用状況、土地の明け渡しの条件として又は土地の明け渡しと引き換えに財産上の給付をする旨の申出をした場合における申出を考慮して正当な事由がある場合に認められます。
③借地権消滅後の使用継続による更新:
借地権の存続期間満了後、借地権者が土地の使用を継続するときは、建物がある場合に限り、従前と同じ条件で更新したものをみなします。設定者が遅滞なく異議を述べた場合は更新したものとみなされません。※
※②の異議と同様
④滅失建物の再築による更新:
借地権設定者の承諾があった日又は建物が築造された日から20年。
但し、借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき、借地権設定者の承諾がある場合に限ります。
また、借地権者が設定者に残存期間を超えて存続する建物を新たに築造する旨を通知した場合、設定者が通知を受けた後2か月以内に異議を述べないときは、承諾があったものとみなされます。
・借家契約の更新についての修正
①期間満了前に賃貸人から更新拒絶の通知のない場合の更新:
建物の賃貸借に期間の定めのある場合に当事者が期間満了日の1年前から6か月前までの間に契約を更新しない旨又は変更する旨を通知しなかったときは従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
②使用の継続に対して賃貸人が異議を述べない場合の更新:
①の通知をした場合に建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べないときも契約を更新したものとみなされます。
(2)改正のポイント
・賃貸借の存続期間
最長期間: 50年に変更
最短期間: 旧法と同じく制限なし
例 外 : 旧法と同じく短期賃貸借
※期間の定めのない場合は解約申入れされた後、次の猶予期間が認められます。
土地:1年 建物:3か月 動産:1日 (617条)旧法と同じ
・借地権の存続期間、借家権の存続期間、契約の更新
以上のものにつきましては、旧法とおなじ取り扱いになります。
2.賃貸人の地位に関する改正点

(1) 賃貸人の地位の移転の明文化(新605条の2第1項新設)
・賃借権の対抗力と賃貸人の地位の関係
・賃借権が対抗力を有する場合
不動産賃貸借において、賃借物の所有者たる賃貸人が賃借物を譲渡した場合、賃借人が譲受人に賃借権を対抗できることを要件に、また、賃借人の承諾なしに(譲渡人・譲受人間の合意も不要)、賃貸人たる地位が当該賃借物の譲受人に移転します。
これは、今回の民法改正によって、従来形成されていた判例法理の流れに従って明文化されたものです。
それとともに譲受人が新賃貸人であることを賃借人に対抗するためには、譲受人が賃貸不動産の対抗要件を備える必要があることも明文化されます。
・賃借権が対抗力を有しない場合
賃借権は、賃貸人に対して賃料と引き換えに賃借物を使用収益させることを求める債権であることから、賃借人は譲受人に自己の賃借権を主張することができないため、目的不動産の譲受人は、賃貸人たる地位を承継しなくても、賃借人に対して明渡請求をすることができます。
ただし、賃借権に対抗力がない場合であっても、譲渡人・譲受人間で合意されれば、その際賃借人の同意なしに譲受人が賃貸人たる地位を承継することができます。(新605条の3)
また、譲受人から明渡請求が認められた場合には、賃借人は譲渡人に賃貸借契約の履行不能に基づく損害賠償請求ができる点にも注意が必要です。
・明文化に影響した判例
①【大判大10・5・30】<不動産賃借権の内容> 旧所有者と賃借人との間に存在した賃貸借関係が法律上当然に新所有者と賃借人との間に移転し、旧所有者は、その関係から離脱する。
②【最判49・3・19】<賃貸人の地位の移転の賃借人に対する対抗要件> 賃貸中の土地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しなければ、これを賃借人に対抗することができず、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
③【最判昭44・7・17】<敷金返還債務の承継>※ 賃貸借存続中に目的不動産の所有権が移転し、新所有者が賃貸人の地位を承継した場合には、旧賃貸人に差し入れられていた敷金は、同人のもとに未払賃料があればこれに当然充当され、残額があればそれについての権利義務が新賃貸人に承継される。
④【最判昭48・2・2】賃貸借終了後に明渡し前に、目的不動産の所有権が移転した場合は、敷金に関する権利義務は、旧所有者と新所有者の合意のみで新所有者に承継されない。
(注)改正前民法の判例法理の③については、実務では、賃料債務等の債務額が敷金から充当されたうえで、その残額について、敷金の返還を請求するといった処理はされていないという批判があるため、「譲受人が承継する敷金返還債務の範囲」については、明文化されず、今後も解釈または個別の合意に委ねるものとされています。
(2)賃貸人の地位の留保の明文化
・賃貸人の地位の留保の要件(新605条の2第2項新設)
賃貸人が賃借物を第三者に譲渡しても、次の要件を満たせば、譲渡人に賃貸人の地位が留保されます。
- 第三者との間で賃貸人たる地位が譲渡人に留保される旨の合意
- 譲受人と譲渡人との間で別個の賃貸借契約
つまりは、
譲渡人と譲受人の間:賃貸借関係が成立
譲渡人と賃借人の間:転貸借関係が成立
これらも賃貸人の地位の移転と同様に従来の判例の法理に従って明文化されたものですが、従来の判例では、譲渡人と譲受人の賃貸借が解除された場合に賃借人の地位が脅かされてしまうという問題点が生じてしまうため、今回の改正によって、「譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転する」という賃借人の地位の不安定化を回避する条文が規定されました。
・明文化に影響した判例
①【最判平成11・3・25】自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物の所有権を第三者に移転した場合に、新旧所有者間において賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに賃貸人の地位の新所有者への移転を妨げるべき特段の事情があるものということはできない。
新605条の2第2項
前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
参考文献:有斐閣判例六法
3.不動産の賃借人の妨害排除請求権の明文化

(1)不動産賃借人の妨害排除請求権の要件(新605条の4)
不動産の賃借人が次のいずれかの対抗要件を具備したとき、不動産賃借権に基づく妨害排除請求権、返還請求権が認められます。
- 賃借権の登記
- 土地上に借地権者が登記されている建物を所有 ※
- 建物の引渡し(建物の賃貸借)
※建物滅失の場合
滅失すれば、建物所有権は消滅するから、登記簿の記載は無効な登記となってしまいます。但し、次の要件を満たせば2年間まで対抗力を維持することができます。
- 滅失の日と新しい建物を築造する旨をその土地上に掲示すること
- 滅失後、2年以内に、新しい建物を築造してその旨の登記をすること
これは、改正前民法下で二重賃借人、不法占拠者に対する関係で対抗力のある不動産賃貸借に妨害排除請求権を認めた従来の判例を明文化したものです。
また、新605条の4による請求には対抗要件が必要とされているが、対抗要件を備えていない場合でも不動産賃借権を保全するために賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することはできる点に注意が必要です。
(2)賃借権の対抗力に関する判例
・上記明文化に影響した判例
①【最判昭28・12・18】 対抗力ある土地賃借権を有する者は、その土地につき二重に賃借権を得た第三者に対し妨害排除を請求できる。
②【最判昭30・4・5】 対抗力ある借地権者は不法占拠者に対して直接に建物の収去・土地明け渡しをすることができる。
・他、借地権に関する重要判例
①【最判昭30・9・23】一筆の土地の全部の借地権者が自己名義で登記された建物を所有するときは、その後に当該土地が分筆されて、建物の登記が存在しない土地が生じても、その土地について借地権の対抗力が失われることはない。
②【最判昭40.3.17】借地権者が借地上に有する建物の登記が、錯誤又は遺漏により、地番等について実際と相違がある場合でも、建物の種類、構造、床面積等の記載から同一性を認識できる軽微な誤りであり、たやすく更正登記をすることができるときには、借地権を対抗することができる。
③【最判昭40・6・29】二筆以上の土地の借地権者が、自己名義の建物をそのうち一筆の土地上に所有しているにすぎない場合、たとえその建物の庭として一体のものとして使用していても、その他の土地には借地権の対抗力が及ばない。
④【最判昭41・4・27】借地権者は借地上に家族名義で所有権保存登記をした建物を所有している場合、借地権の対抗力は認められない。
⑤【最判昭50・2・13】借地権者が、自己を所有者とする表示の登記をした建物を所有している場合、借地権の対抗力が認められる。
新605条の4
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
- その不動産の占有を第三者が妨害しているときーその第三者に対する妨害の停止の請求
- その不動産を第三者が占有しているときーその第三者に対する返還の請求
参考文献:有斐閣判例六法
4.敷金に関する改正点

改正前民法下では、敷金の定義や敷金返還請求権の発生時期や請求範囲、敷金の充当について明文規定がなく、すべて判例や解釈により取り扱われていました。
今回の民法改正によって、判例、解釈に委ねられていた点がすべて明文化されました。
(1) 敷金の意義(新622条の2)
敷金とは・・・いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭を指します。
※要件に該当すれば、当事者間で別名で呼ばれているものであっても新622条の2の適用を受けます。
(2)敷金返還請求権の明文化
・発生時期
- 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
- 賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき
①に関して敷金返還債務と賃借物の返還債務は同時履行の関係にはなく、返還債務が先履行になります。
②に関して賃借権の譲渡があった場合には旧賃借人が差し入れた敷金は新賃借人に承継されない点に注意が必要です。
・請求の範囲
返還する額= 敷金 ― 賃貸借に基づく賃借人の賃貸人に対する金銭給付
を目的とする債務の額 ※
※具体例としては、未払い賃料や損害賠償などがこれにあたります。
・敷金返還請求権に関する判例
①【最判昭48・2・2】<返還請求権の範囲>
敷金は賃貸借終了後目的物の明渡義務履行までに生ずる損害金その他賃貸借契約関係により賃貸人が賃借人に対し取得する一切の債権を担保するものであるから、その返還請求権は、目的物明渡し完了の時にそれまでに生じた右被担保債権を控除し、なお残額がある場合にその残額につき発生する。
②【最判昭53・12・22】<賃借権が譲渡された場合>
賃貸人の承諾を得て賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転された場合でも、敷金に関する権利義務関係は、敷金交付者と賃貸人の間で敷金をもって新賃借人の債務の担保とすることを約し、又は新賃借人に敷金返還請求権を譲渡するなどの特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。
③【最判平10・9・3】<敷引特約された目的物の滅失>
居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、敷引特約※がされた場合であっても、災害により賃借家屋が滅失し、賃貸借契約が終了したときは、特段の事情の無い限り、敷引特約を適用することはできず、賃貸人は賃借人に対し、敷引金を返還すべき義務を負う。
※敷引特約・・・賃貸借終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金具(敷引金)を返還しない旨の特約
(3)敷金の充当の明文化
・敷金の充当
・賃貸借契約存続している場合
不履行に陥った賃料債務等については、賃貸人は敷金をその弁済に充てることができます。
一方、債務者である賃借人が担保を減少させることはできないという趣旨から賃借人が敷金を延滞賃料などの弁済に充当するように賃貸人に請求することはできません。
・賃貸借契約が終了し目的物が返還された場合
賃貸人は敷金の額から賃借人の金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
・賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合
賃貸人は敷金の額から賃借人の金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
・敷金の充当に関する判例
①【大判大15・7・12】
賃貸借が終了した場合、賃料の延滞があるときは、当然敷金から充当される。
②【大判昭5・3・10】
賃借人が賃料の支払を怠ったときは、賃貸人は賃貸借の存続中であっても、敷金を賃料の支払に充当できるが、賃借人側からは充当することは主張することはできない。
新622条の2第1項
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
- 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
- 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき
第2項
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
参考文献:有斐閣判例六法
5.賃借物の一部滅失による賃料の減額等

賃料は賃借物が賃借人の使用収益可能な状態に置かれたことの対価として日々発生するものであるから、賃借物の一部滅失によってその使用収益が不可能になったときは、賃料もその一部の割合に応じて当然に発生しないと考えるべきであり、賃借人からの請求を要するのは妥当ではないとして、今回の民法改正によって、減額請求は不要とし、当然に減額される規定が設けられました。
また、賃料が使用収益の対価であるという趣旨から賃借物の「滅失」の場合にだけ限定されるものではなく「使用及び収益をすることができなくなった場合」にも、賃料の減額がなされる規定が設けられています。
(1)旧法のおさらい
一部滅失が賃貸人の帰責事由による場合
賃貸人の債務不履行により処理されるのではなく、旧611条が適用されるため、賃借人は滅失した割合に応じて賃料の減額請求ができます。
※滅失には、賃貸目的物の滅失だけでなく、他の物の滅失で賃借物の利用価値が減少する場合も含みます。
一部滅失が賃借人の帰責事由による場合
旧611条の適用はなく、旧536条2項の危険負担の問題となります。
一部滅失につき、双方の帰責事由がない場合
危険負担で処理されるのではなく、旧611条が適用されるため、減額請求があってはじめて減額されます。
また、賃借物の滅失部分が修繕可能な場合には、賃借人は修繕請求権と賃料請求権の双方を行使でき、修繕完了まで賃料を減額することを請求しうる。
解除権
賃借人は、目的物の一部滅失により残存部分では賃貸借の目的を達成するのが不可能なときには、解除することができます。
関連する判例
①【最判昭43・11・21】
居住にある程度の支障ないし妨害はあったが、使用収益を不能又は著しく困難にするほどの支障はなかった場合、家屋の賃借人は、賃料の全額について支払を拒むことはできない。
(2)改正のポイント
一部滅失につき、賃借人に帰責事由がない場合
旧法で必要であった減額請求は不要となり、使用収益部分に応じて当然に減額される。
賃借人に帰責事由がないことの証明責任は、賃借物が賃借人の支配下にあることから賃貸人が賃借人の帰責事由の有無を把握することは困難であるため
賃借人側が、証明責任を負うとされています。
一部滅失につき賃借人に帰責事由がある場合
賃料は減額されません。また、賃貸人は新415条に基づき、賃借人に損害賠償請求をすることができます。
解除権
賃借人は目的物の一部滅失等により、残存部分では賃貸借の目的を達し得ない場合には、契約を解除できます。
(注)賃借人に帰責事由ある場合であっても解除することができます。
賃借人の帰責事由による差異のまとめ
| 帰責事由無 | 帰責事由有 | |
| 賃料減額の有無 | 〇 | × |
| 賃貸人の修繕義務の有無 | 〇 | × |
| 必要費償還請求権の有無 | 〇 | × |
| 賃借人の原状回復義務の有無 | × | 〇 |
新611条1項
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2項
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
参考文献:有斐閣判例六法
6.全部滅失による賃貸借終了に関する規律の明文化

(1)賃借物の全部滅失による賃貸借の終了
賃借物の全部が滅失した場合等には、賃貸借契約の目的を達成することが不可能であるにもかかわらず、契約の解除をしない限り賃料債務が発生するのは不当であることから賃借物の全部が滅失し、使用収益することができない場合には、賃貸借は当然に終了するという判例法理を明文化したものが規定されました。
(2) 明文化に影響した判例
①【最判昭32・12・3】
賃貸物の目的物たる建物が朽廃しその効用を失った場合は、目的物滅失の場合と同様に賃貸借の趣旨は達成されなくなるから、これによって賃貸借契約は当然に終了する。
②【最判昭42・6・22】
賃貸借の目的である家屋が火災によって滅失したか否かは、賃貸借の目的となっている主要な部分が消失して賃貸借の目的となっている主要な部分が消失して賃貸借の趣旨が達成されない程度に達したか否かによって決めるべきであり、それには消失した部分の修復が通常の費用では不可能と認められるかどうかも斟酌すべきである。
新616条の2
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
参考文献:有斐閣判例六法
7.賃借人の原状回復義務の明文化

改正前民法においては、原状回復義務については具体的な規定は設けられておらず、収去義務について、旧616条にて、使用貸借の旧594条(使用収益上の義務)、旧597条(借用物の返還時期)、旧598条(収去義務)が準用されていました。
今回の改正によって、新616条が準用するものは新594条(使用収益上の義務)のみとなり、原状回復義務については、従来の判例法理に基づき、あらたに新621条において明文化されました。
(1)原状回復義務
賃借人に帰責事由がある場合
原則:原状回復義務を負う。
例外:賃借物の通常損耗、賃借物の経年変化は除く
例外の例外:賃借人の明確な合意のもと通常損耗の回復義務を負う旨の特約
※賃借人が原状回復義務を履行しない場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。
賃借人に帰責事由がない場合
原則:原状回復義務を負わない。
(注)賃借人に帰責事由のないことの立証責任は賃借人が負います。
通常損耗に当たる具体例
- 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
- テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ、
- 鍵の取り換え(破損、紛失のない場合)
原状回復義務に関する判例
①【最判平17・12・6】<賃借人の回復義務に関する特約>
賃貸借契約においては物件の損耗の発生は本質上当然に予定されているものであるので、通常損耗についての原状回復義務を建物賃借人に負わせる旨の特約は、賃借人が費用負担をすべき通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されているか、賃貸人が口頭で説明し賃借人がそれを明確に認識して合意の内容としたと認められるなど、明確に合意されていることが必要である。
②【最判平23・3・24】<敷引特約の有効性>
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は、通常損耗等の修繕費用を賃借人に負担させる趣旨を含むが、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り消費者契約法10条により無効となる。
新621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
消費者契約法10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
参考文献:有斐閣判例六法
8.転貸の効果に関する整備・明文化

(1)転借人に対して行使可能な権利の範囲の明確化
今回の民法改正によって、旧613条1項に「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として」という文言が追加され、賃貸人に対する転借人の「転貸借に基づく債務」の内容とその限度が明らかにされました。(新613条)
「転貸借に基づく債務」とは
賃料債務だけではなく、目的物返還義務、目的物保管義務、また、転借人が目的物を滅失、損傷した場合には損害賠償義務も含まれます。
※転借人は賃貸人に対して権利を有しないため、適法な転借人は、修繕要求や有益費の償還請求はできません。
転借人における「賃借人の債務の範囲の限度」
賃貸人に対しての賃料:転借料と賃借料の双方の範囲内
賃貸人に対しての支払時期:転借人・賃借人双方の債務の弁済期が到来した時点
承諾転貸における転貸人、転借人間の法律関係
原則:通常の賃貸借契約と同様に扱われる。
(注)転借人が賃貸人に対して負う義務を直接履行すれば、その限度で賃借人に対する義務を免れます。
承諾転貸における原賃貸借の賃貸人・賃借人間の法律関係
原則:転貸借の影響を受けない。
例外:転借人が目的物を滅失、損傷させた場合、賃借人は賃貸人に対して責任を負う。
(2)合意解除の転借人に対する関係の明文化
合意解除による終了
賃貸人と賃借人が合意解除 ⇒ 転借人に対抗不可
その結果としては、原賃貸借契約存続説と直接関係肯定説という2つの学説に分かれます。
原賃貸借契約存続説:転貸借関係は存続し、原賃貸借関係もその限度で存続します。
直接関係肯定説:原賃貸借関係は合意解除により消滅したことを前提として、原賃貸人と転借人が直接の賃貸借関係に立ちます。
債務不履行解除による終了
賃借人の債務不履行による解除 ⇒ 転借人に対抗可
転貸借の終了時期:賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時
期間満了による終了
期間満了による終了 ⇒ 転借人に対抗可
転貸借の終了時期:賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時
例外: 借地借家法の適用がある場合(借借34条)
賃貸人は賃貸借の終了を転借人に通知しなければ、転借人に賃貸借の終了を対抗できません。
通知が適切になされた場合には、転貸借は通知がなされた時から6か月を経過すると終了することになります。
承諾転貸に関する重要判例
①【大判昭9・3・7】
賃貸人と賃借人が合意解除しても、賃貸人は解除をもって転借人に対抗することはできない。
②【最判昭36・12・21】
賃借人の債務不履行により賃貸借が解除されたときは、転貸借履行不能により終了し、転借人は賃貸人に対抗することができない。
③【最判昭37・3・29】<転借人への催告の有無>
賃料の延滞を理由として賃貸借を解除するには、賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、転借人にその支払の機会を与える必要はない。
④【最判昭48・10・12】<賃借人の破産の場合>
賃借人会社の代表者である賃貸人が、自己の都合により転借権を消滅させるため、賃借人会社を代表してその自己破産を申し立て、破産宣告を得た上、これを理由として賃貸借契約を解除することは、転借人に対し著しく信義則に違反する行為であって、転借権は消滅しない。
⑤【最判昭38・2・21】<土地賃貸借の解除と建物の賃借人の地位>
土地の賃貸人と賃借人が土地賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情のない限り、土地の賃貸人は解除をもって賃借人の所有する地上建物の賃借人に対抗することはできない。
9.賃貸借における損害賠償等についての期間の制限

新622条において、使用貸借の600条の規定を準用しているため、趣旨は使用貸借と同様になります。
貸主が目的物を貸している期間中、貸主が目的物の状況を把握することは難しいため、借主に対する用法遵守義務違反に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかってしまうという不都合な事態になってしまうため、新600条2項において、契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害賠償請求権に時効の完成の猶予が認められると規定されました。
新622条⇒600条準用
新600条1項
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
新600条2項
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
参考文献:有斐閣判例六法
まとめ

改正点としては、全体的に明文化したものがほとんどであり、そうではなく、新設されたものを注意深く読み込めば充分な分野ではないと考えます。